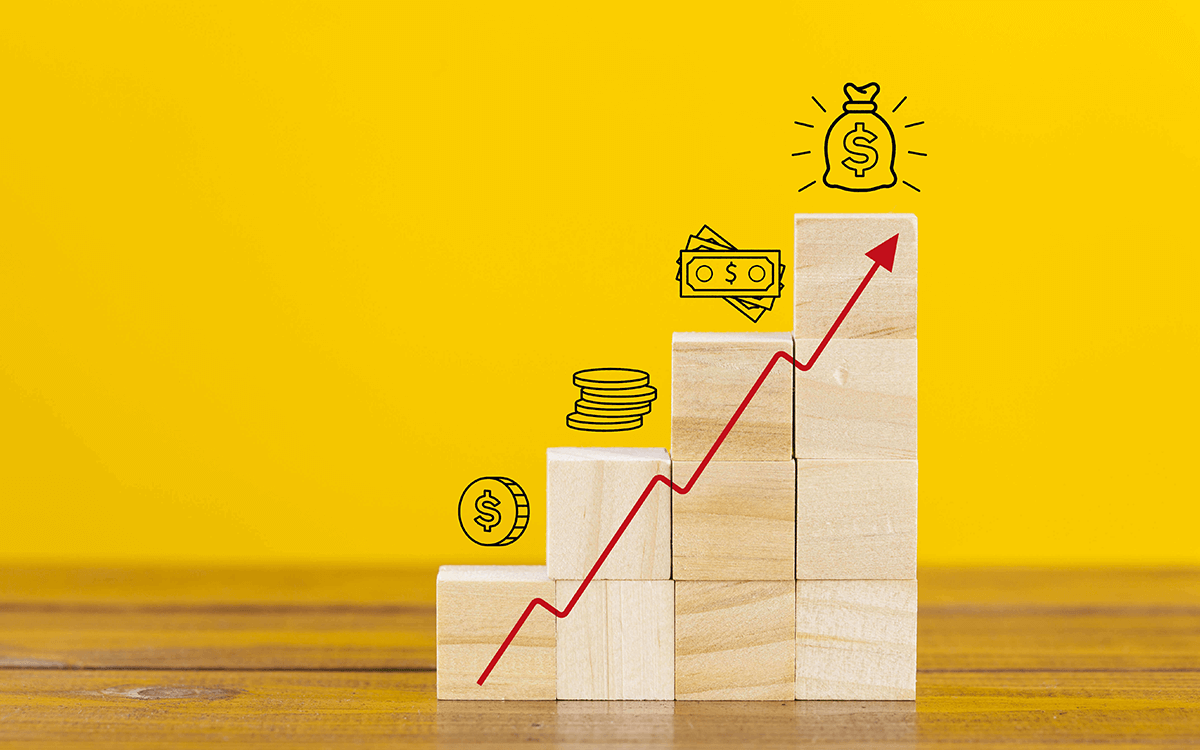Uber Eatsのこれまで
日本にUber Eatsが来たのは2016年9月のことです。東京の渋谷区と港区でスタートしました。
その後23区エリア全体でサービスが始まり、大阪や京都、福岡、愛知などに進出。2018年の年末ごろから爆発的な人気が出てきました。それからというもの、右肩上がりで成長を続けるUber Eatsですが、将来どのようなことが考えられるのでしょうか。
Uber Eatsの拡大
現在展開されている都道府県は人口が多い順に開始されており、2020年1月時点で東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県で対応しています。
この中に北海道が入っていない理由は、人口は多いのですが密集していないためだと予想されています。密度の高さで今後展開されるだろう地域を予想していくと、広島市、堺市、相模原市、北九州市、仙台市で開始されるのではないかと予測されています。
まだかまだかと首を長くして待っているお客さんもいますので、今後も拡大は進んでいくとされています。
Uber Eatsの課題
拡大を予想されているUber Eatsには、課題もたくさんあります。
配達員とUber Eatsの関係性は雇用関係ではなく、個人事業主に依頼をしているような形です。その関係性の中で起きるトラブルについて、SNSやネットニュースなどで大きく取り上げられたこともありました。Uber Eatsファンからすると、この課題に対する今後の対応次第で、支持するかどうかを判断していくポイントになりそうです。
海外のUber Eatsでは
もともとは海外からスタートしたUber Eats。フードデリバリー市場では、グラブハブやドアダッシュに続いて展開を始めた、第三の参入企業になります。2016年に日本で展開を始めるまでは、距離報酬が150円ほどあったそうです。日本参入に伴い、単価を60円引き下げ12%カットされてしまいました。そのため、配達員が急激に減り料理が届けられない・時間超過でマイナス評価を付けられるような状態が起きてしまったのです。
ただ、注文した料理を配達してほしいと思っているお客さんや作った料理を届けて欲しいというお店は増える一方なため、Uber Eats日本法人が今後どういった対応をしていくかにも注目が集まっています。
また、Uber Eatsは第三の参入企業として日本でも展開をしていますが、宅配事業市場はまだまだ拡大をしています。競争の激化は免れず、少なからず影響を受けていくことが考えられます。
Uber Eats配達員としては、単価の引き下げや規模の縮小などは避けて、活躍しやすい体制を築いていって欲しいというのが本音なところです。